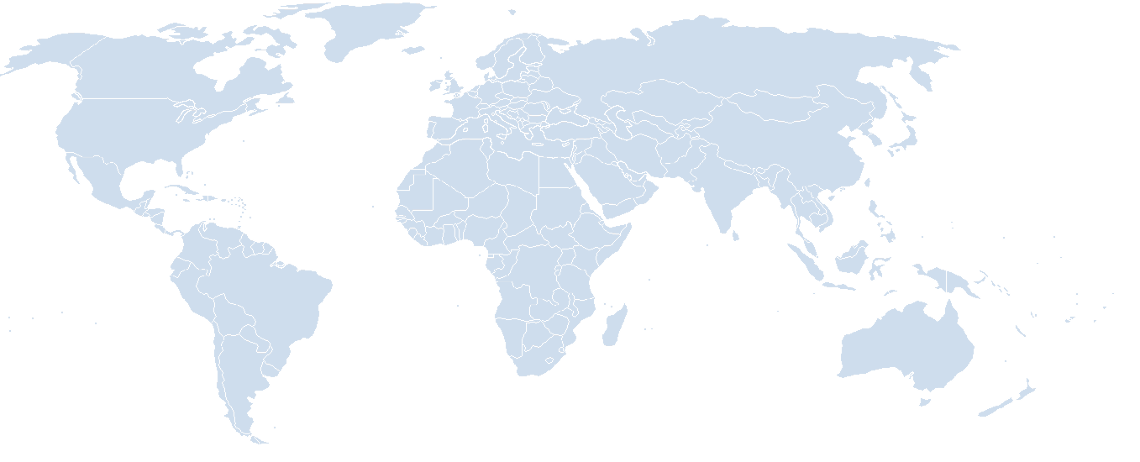起亜、ハイブリッド車販売2倍へ EV逆風で戦略修正
韓国レポート
韓国現代自動車グループがハイブリッド車で攻勢を掛ける。傘下の起亜は主要9車種でHVモデルを新たに投入し、2028年までに販売台数を80万台と現状の2倍に増やす計画だ。世界的に競争が過熱するEVへの重点投資を一旦見直し、市場動向に柔軟に対応する。
「需要の減速、競争の加速だ」。4月上旬、起亜がソウル市内で開いた経営戦略説明会でCEOは焦りをにじませた。EV市場の失速を認め、2026年としていたEV販売台数100万台突破の目標を2027年に延期した。
同時に打ち出したのはHVの拡大だ。2028年までに世界の主要モデル9車種でHVを発売する。HVの販売台数を2024年の37万2000台(全体の12%)から80万台(19%)に増やす。
2023年の起亜の新車販売台数は301万台。うち韓国国内は2割弱。欧米が販売の5割を占める。HVも国内に加え、欧米市場を中心に販売拡大を目指す。
製造体制も販売戦略の転換に対応する。起亜は国内外の13工場でEVとHV、エンジン車のいずれも製造する「混流生産」を手掛け、製造比率を柔軟に変動させることができる。
さらに、研究開発費を積み増す。2028年までの今後5年間で既存の5カ年(2023〜2027年)計画に比べ5兆ウォン(約5600億円)増やし、38兆ウォンを投資する。HV向けの新しいエンジン開発を進めている。省エネ機能を高め、最大走行可能距離を伸ばすなどする。
韓国自動車モビリティ産業協会によると、2023年の韓国内の新車販売はEVが前年比6%減の11万6000台に落ち込んだ。一方HVは55%増の28万台だった。金利上昇や充電設備の不足でEV消費が伸びず、手ごろで燃費も良いHV人気が高まっている。
参考: 日経
PSR 分析: これまで現代グループに代表される韓国勢はEV一辺倒の戦略でシェアを伸ばしてきたが、市場の変化に対応すべく大きな戦略転換を行う。これまでハイブリッド車は欧州などが中心となって市場から排除しようする動きがあった。その一方で、BEVが持つ弱点を市場が徐々に認知したことでハイブリッドの良さが見直されつつある。特にBEVは中国のEV車の供給過多などが報道されるなど、需要に陰りが見られている。こうした市場の変化に柔軟に対応するという意味で今回の起亜の戦略転換は高評価されるだろう。
ハイブリッド技術はトヨタを筆頭に日本勢が技術的にリードしており、韓国勢が追い付くためには大規模な投資が必須となる。すぐに追いつけるほど小さな差ではないだけに、韓国ブランドが世界市場で存在感を維持拡大していくためには、この方針転換に基づいた迅速なアクションが求められるだろう。PSR
小室 明大 – 極東及び東南アジア リサーチアナリスト