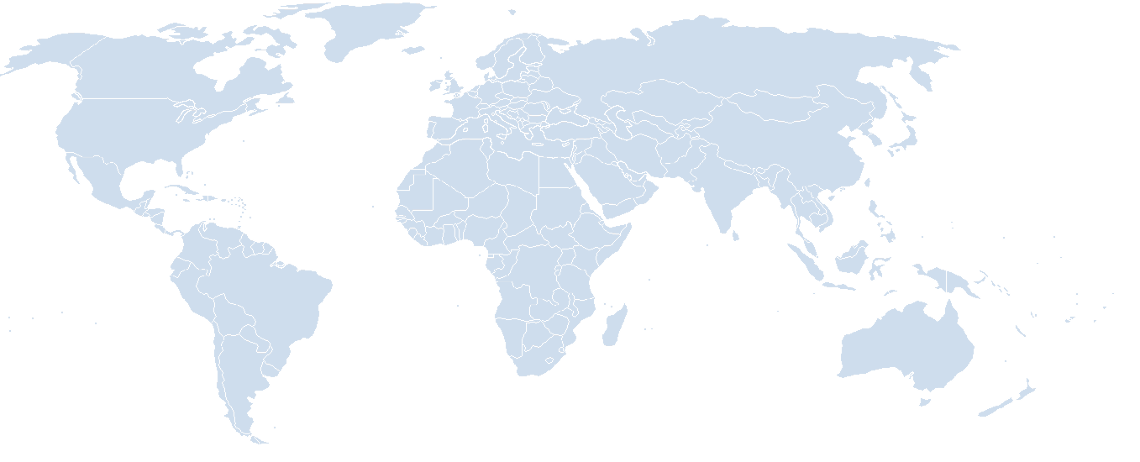コマツ、運べる水素発電機 電動ショベル向け
日本レポート

4月23日、コマツは水素を燃料とする発電機を開発したと発表した。電動ミニショベルの給電に使う。作業現場まで持ち運べて、電力のインフラがない場所でも電動建設機械を使えるようになる。発電時に排出するCO2を最大40%削減し、建設現場の脱炭素につなげる。2024年9月までに顧客の現場で実証実験する。デンヨーが協力して開発した。発電機の大きさは長さ3.1メートル、幅1.1メートル、高さ1.7メートル。軽油に水素を最大40%混ぜて発電する。廃食油などを使ったバイオ燃料の一種「HVO燃料(水素化植物油)」も使える。
水素混焼発電機については、コマツはこれまで工場の自家発電などに使う設置式を開発してきた。同社は7種類の電動建機を扱っているが、配電網が整備されていない現場には電力を届けられず、電力供給インフラの製品化を進めていた。
参考: 日経