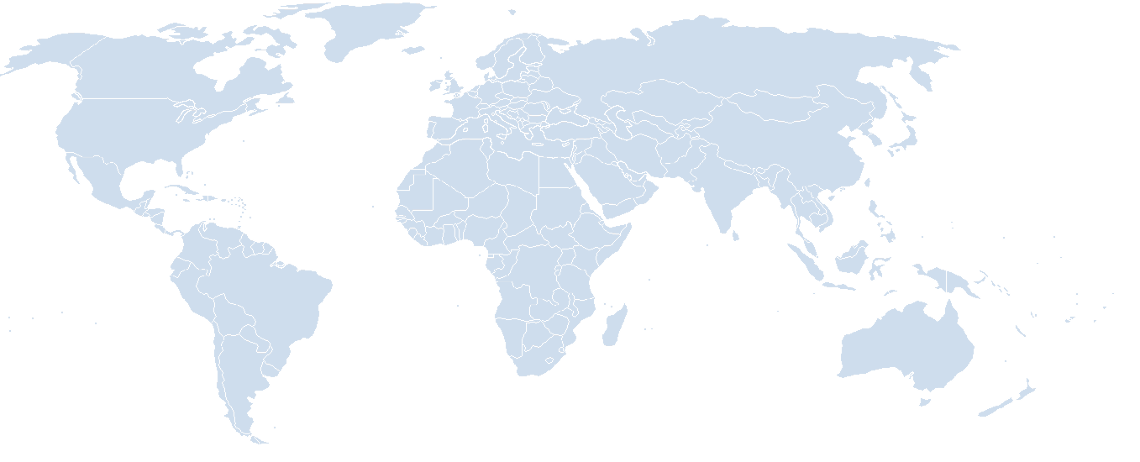国内二輪出荷、2023年は4%増 原付2種が好調
日本レポート
2023年の国内二輪出荷台数は前年比4%増の37万6720台で2年ぶりに増加した。維持費が比較的安い原付き2種が好調で、前年比47%増だった。半導体不足や物流の混乱が緩和したことも出荷増に寄与した。
排気量別では原付1種(50cc以下)が29%減の9万2824台だった。原付2種(50cc超125cc以下)が47%増の14万9655台、軽二輪車(125cc超250cc以下)は16%増の6万6630台、小型二輪車(250cc超)は6%減の6万7611台だった。